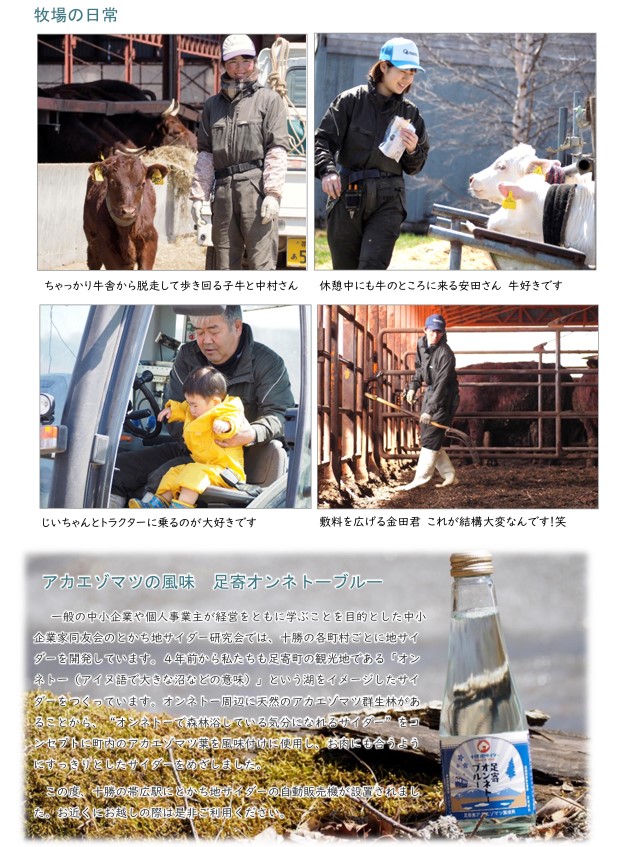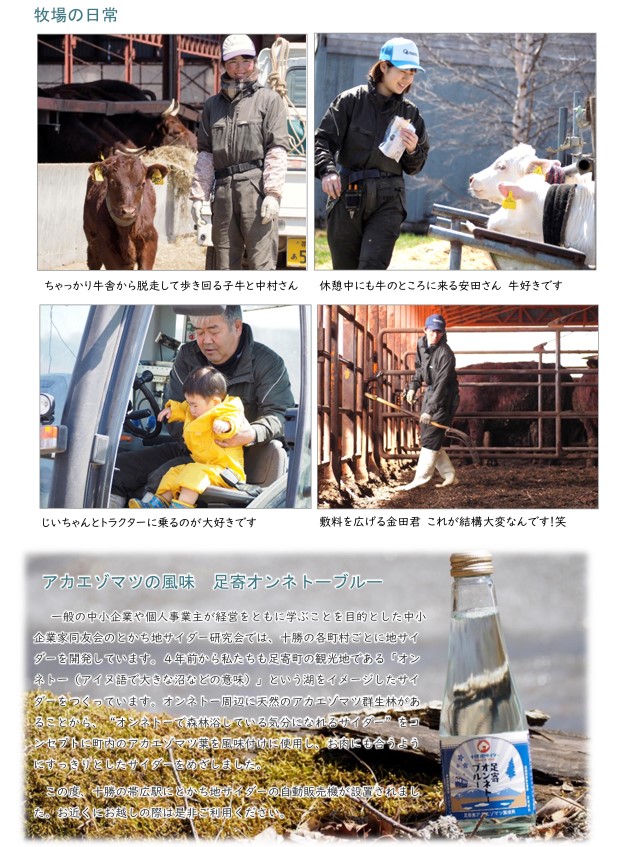デントコーン蒔き付けの準備を進めています今年は雪解けが早かったので、トラクターがぬかるむことなく畑に入れるようになってからは、暦を見ながら土を動かせる日に注意しつつ順調に畑作業を進めています。
しっかり切り返しをし、良い具合に発酵した堆肥をマニアスプレッターという専用の農機に入れてトラクターでけん引し、畑に均等に撒きます。
良く発酵した堆肥は匂いも少なく、菌バランスの良い堆肥は、土に良い働きをし、作物に栄養を与えると同時に、作物に病気が出るのを防ぎます。
デントコーンの連作でも病気が出ずに、しっかり育つことを驚かれる方もいらっしゃいます。
子牛の分娩も50頭を超えました年間の分娩予定頭数は200頭程度を計画しています。
今年も4月中に50頭を超え、おかげさまで事故も少なく順調です。
日本の牛の繁殖は99.9%が人工授精(または受精卵移植)で行われていますが、私たちの牧場では夏山冬里と呼ばれる短角牛の使用方法にあった“まき牛(種牛を雌牛の群にはなすこと)”による自然交配(本交)での繁殖のため、人間が雌牛の発情を管理しなくても自然と妊娠してくれます。
一方で、人工授精では受精のタイミングが把握できるため、分娩の時期も約280日(大体人間と同じくらい)という在胎期間を逆算して把握することができますが、まき牛ですと本交の一瞬のタイミングを目撃しないかぎり、人工授精のようにある程度定まった分娩日を把握することができません。
まき牛の期間からその群のおおよその分娩時期を予測し、あとは日々の雌牛の体型の変化や行動に目を光らせ、分娩をサポートしています。これも中村さんをはじめとした現場の技術の一つです。
分娩を察知したら、バスタオル1枚とフェイスタオル2枚、うがい薬や生菌剤を抱え、母子の元に駆けつけます。
母牛の乳房をタオルできれいにし、前絞りで母牛の乳質を確認してから、子牛が母牛の乳を上手に飲めるように手助けします。
産まれたばかりで羊水で濡れた子牛をバスタオルで拭くのですが、これは体の乾燥を早めるのと同時にマッサージ作用で子牛の血行促進をし立ち上がりを早め、母牛の初乳からの免疫抗体をできるだけ早く子牛に取得させるためです。
ワクチネーションや化学的薬剤に頼らずに元気な牛を育てるためには、この分娩時のサポートがとても大きく関係していると感じま
す。
子牛を拭いていると、母牛がヒトのことも舐めてくれる…ねぎらってくれてるの?私のことはいいから子牛を舐めてちょうだい、母牛とそんなやりとりをしています。